「フフって、どこの国の料理なんだろう?」そんな素朴な疑問から、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。フフとは、ガーナやナイジェリアを中心とした西アフリカの国々で広く食べられている主食のひとつ。キャッサバやヤムイモなどを練り上げて作られるその独特な食感と、濃厚なスープと一緒に“手で食べる”という文化的スタイルが、世界中の食文化愛好家から注目を集めています。
とはいえ、「本場のフフって日本でも食べられるの?」という疑問を持つのも自然なこと。じつは東京都内を中心に、現地出身者が運営する本格アフリカ料理店が少しずつ増えており、フフを体験できるチャンスは意外と身近にあるのです。
この記事では、「フフとはどこの国の料理なのか?」という基本情報から、日本国内で味わえるおすすめ店3選をピックアップし、味・雰囲気・文化体験の視点から詳しく紹介していきます。これを読めば、きっとあなたも“食べる旅”へ出かけたくなるはずです。
①フフとはどんな料理?どこの国が発祥?歴史的背景や専門協会や定義などを徹底解説
「フフとはどこの国の料理なのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
もちもちとした弾力と淡白な味わいが特徴のこの主食は、近年では日本国内でもアフリカ料理店を中心に提供され、SNSでも話題になりつつあります。しかしそのルーツや歴史、正しい定義については、まだ広く知られていないのが現状です。
ここでは、フフとはいったいどんな料理で、どこの国が発祥なのか。その歴史的背景から、現地での食文化、さらには専門協会や定義についても徹底的に解説していきます。
● フフとは?西アフリカを代表する主食
まず「フフ(Fufu)」とは、西アフリカ諸国を中心に食べられている伝統的な炭水化物系主食です。キャッサバ、ヤムイモ、プランテイン(料理用バナナ)などのでんぷん質の食材を茹でて、すりつぶして、粘り気が出るまで練り上げたものです。日本でいう「餅」に近い食感であり、濃い味付けのスープやシチューと一緒に手でちぎって食べるのが基本スタイルです。
「フフとはどこの国の料理なのか」という問いに対しては、複数国にまたがって根づいた食文化であるというのが答えです。特に、ガーナ、ナイジェリア、コートジボワール、トーゴ、ベナンなどがフフの代表的な食文化圏とされています。
● フフの発祥と歴史的背景|奴隷貿易と農作物の伝播
フフの正確な「発祥地」を特定するのは難しいものの、歴史的にはガーナとナイジェリアが主要なルーツとされています。起源は数百年前にさかのぼり、**西アフリカのアカン族(現在のガーナ周辺)**の食文化から発展したといわれています。
フフの歴史を語るうえで欠かせないのが、16〜19世紀にかけての大西洋奴隷貿易です。この時代、多くのアフリカ人がアメリカ大陸に連行され、その際に彼らが慣れ親しんだ作物や調理法も一緒に運ばれました。その中にはキャッサバやプランテインなど、現在フフの主原料となる作物が含まれていました。
このようにして、フフのような「すり潰す・練る」という調理法はカリブ海諸国や中南米にも伝播していきます。現在でもドミニカ共和国やハイチでは、「マンゴ」「ムファンゴ」などの似たような料理が食べられており、それらはフフの食文化的な“遠い親戚”とも言える存在です。
● フフの食文化と社会的な役割
フフとは単なる主食ではなく、西アフリカにおいては**「食卓の中心」かつ「家庭と地域のつながり」を象徴する存在**です。家族や友人との共同体で食べることが一般的で、大皿に盛られたフフを囲みながら、手でちぎってスープにつけて食べるのが伝統的な食べ方です。
ナイジェリアやガーナでは、結婚式や祭り、葬儀などの重要な儀式や祝事でもフフが欠かせません。特にスープの種類によって意味合いが異なることもあり、「グラウンドナッツスープ」「ライトスープ」「エグシスープ」などとの組み合わせが主流です。
こうした文化背景からも分かる通り、「フフとはどこの国の料理か」と一括りにするのではなく、複数の民族・国・歴史を超えて共存する西アフリカのアイデンティティ的料理だと言えます。
● フフに関する専門協会や国際的な取り組み
意外かもしれませんが、フフに関する明確な「国際認定機関」や「専門協会」はまだ世界的には確立されていません。しかし、近年ではアフリカ料理の再評価とともに、いくつかの非営利団体や民間グループがフフを文化遺産として保存・普及しようとする活動を展開しています。
▷ 例:The African Food Heritage Project(AFHP)
この団体は、アフリカの伝統食文化を国際的に紹介するプロジェクトで、特にフフを「失われつつある伝統食の象徴」として特集。地元の職人とのコラボで調理ワークショップやドキュメンタリー制作なども行っています。
▷ ガーナ・ナイジェリア国内の料理学校・大学
現地の農業大学や観光学部では、「フフ作り」が伝統調理実習として取り入れられており、食文化教育の一環として次世代への継承が行われています。
こうした動きからも、今後「フフに関する正式な基準」や「伝統食品としてのユネスコ登録」などの展開が期待されています。
● フフの定義と分類:料理としての位置づけ
改めて「フフとは何か」を明確に定義づけるとすれば、以下のようにまとめることができます。
フフとは、西アフリカ諸国を中心に食されている、キャッサバ・ヤムイモ・プランテインなどを蒸すまたは茹でて、臼で潰し、粘り気を出した炭水化物系の主食であり、濃厚なスープやシチューに添えて食される料理。
この定義に基づけば、他の似たような料理(例:ケニアのウガリ、中米のマンゴなど)は似て非なるものであり、**フフはあくまで「西アフリカに根づいた、家庭の味」**であると言えます。
また、地域によっても材料や調理方法が異なる点もフフの魅力です。たとえば:
-
ガーナ:キャッサバ+プランテインでやや柔らかめに仕上げる
-
ナイジェリア:ヤムイモを使用し、やや弾力強めの仕上がり
-
コートジボワール:トウモロコシ粉や他の穀物をブレンドすることも
このように、「フフとはどこの国の料理か?」という問いに明確な一国名で答えるのは不正確であり、「西アフリカ全体に広がる共有文化」と理解するのが正しいアプローチとなります。
→第②節フフとは?どこの国の料理?何を使っている料理なのか→具材や食べ方、作り方などを紹介に続く!
②フフとは?どこの国の料理?何を使っている料理なのか→具材や食べ方、作り方などを紹介
「フフとはどこの国の料理なの?」という疑問をきっかけにその魅力を知った人も多いかもしれませんが、実際にフフをどうやって作るのか、何が入っているのか、どう食べるのかについては、まだあまり情報が知られていません。
今回は「具材・作り方・食べ方」に焦点を当てて、より実践的かつ文化的な視点から、フフとはどのような料理なのかを紹介していきます。現地での定番レシピから、日本での再現方法まで、詳しく解説していきましょう。
● フフとは何を使った料理?主な材料とその特徴
フフの主な材料は「でんぷん質の根菜類」です。もっとも一般的なのはキャッサバですが、地域によってヤムイモ、プランテイン(調理用バナナ)、あるいはそれらをミックスしたものが使われます。
▷ 1. キャッサバ(Cassava)
-
南米原産で、アフリカに持ち込まれた主要食材。
-
加熱してすり潰すと、粘りと弾力が出る。
-
食感はややもっちり、味は淡白。
-
現地では「フフの基本」とされる。
▷ 2. ヤムイモ(Yam)
-
アフリカ原産で、糖分は少なく、粘り気は強め。
-
ナイジェリアなどではヤムイモだけで作る「ヤムフフ」が定番。
-
日本の長芋や山芋とは異なり、加熱するとホクホクに。
▷ 3. プランテイン(Plantain)
-
バナナの一種だが甘くなく、煮る・焼くなど加熱して食べる。
-
キャッサバとミックスされることで柔らかく滑らかなフフになる。
-
ガーナでは「プランテイン+キャッサバ」の組み合わせが主流。
このように「フフとはどこの国の料理か」という問いに対して、その国や地域によって材料のバリエーションがあるのが最大の魅力です。材料は異なっても、最終的には「すり潰して練り上げる」という点が共通しています。
● フフの基本的な作り方|現地版と日本版
フフの作り方は、材料を「茹でる」→「潰す」→「練る」という3つのステップを基本に構成されます。
▷ 現地での伝統的な作り方
-
キャッサバやヤムイモを皮ごと茹でる(30〜40分)
-
木臼と杵(モルタル&ペッスル)で熱いうちに叩き潰す
-
何度も折りたたみながら、なめらかで弾力のある状態まで練る
-
丸く成形して大皿に盛りつけ、スープとともに提供
この作業は非常に重労働で、地域によっては家族全員で協力してフフを作ることも珍しくありません。
▷ 日本でできる簡易フフの作り方
日本ではキャッサバやプランテインが手に入りにくいため、**加工済みのフフ粉(Fufu flour)**を使うのが一般的です。Amazonや輸入食材店で購入できます。
-
水を沸騰させ、火を弱める
-
フフ粉を少しずつ加えながら、木べらで手早くかき混ぜる
-
粘り気が出て、もち状になるまで混ぜ続ける(5〜7分)
-
手を水で湿らせて成形し、お椀型に盛りつけて完成
👉 **ポイント:**ダマにならないよう、フフ粉を少しずつ加えて練るのがコツ。電子レンジを使うレシピもあります。
● フフの食べ方|スプーンを使わず“手”で食べるのが伝統的
「フフとはどこの国の料理か?」という文化背景を理解する上で最も印象的なのが食べ方の流儀です。西アフリカでは、フフは基本的に右手のみで食べるのがマナーです(左手は不浄とされるため)。
▷ 食べ方の基本ルール
-
右手でフフを一口サイズにちぎる
-
指先で丸めるように成形
-
スープやシチューに浸し、汁ごと口に運ぶ
-
噛まずにそのまま飲み込む(フフ自体は味が淡白なため)
この「飲み込むスタイル」は初めての人には驚きですが、現地では「噛むと粘りが崩れて美味しさが落ちる」とされており、あえて噛まずに喉越しを楽しむのが伝統です。
● フフと一緒に食べるスープの種類とその意味
フフはそれ自体はほぼ味がなく、合わせるスープやシチューこそが料理の主役とも言えます。以下は現地でよく見られる定番スープです。
▷ 1. グラウンドナッツスープ(Groundnut Soup)
-
ピーナッツをベースにトマト・玉ねぎ・唐辛子などを加えた濃厚スープ
-
ナッツのコクとスパイスが絶妙にマッチし、初心者にもおすすめ
▷ 2. ライトスープ(Light Soup)
-
トマトとスパイスをベースにしたシンプルな赤いスープ
-
魚介やチキンと一緒に煮込むことが多い
▷ 3. エグシスープ(Egusi Soup)
-
メロンの種を砕いたものをベースに作る、ナイジェリアの代表的スープ
-
濃厚かつまろやかな味で、ヤムフフとの相性が良い
▷ 4. パルムナッツスープ(Palm Nut Soup)
-
パーム果実から抽出したオイルとスパイスで煮込む濃厚系
-
独特の風味があり、好みが分かれるが現地では人気
こうしたスープの種類からもわかるように、「フフとはどこの国の料理か」というより、「どのスープと組み合わせるか」によって地域性が現れると言っても過言ではありません。
● 日本でフフを楽しむには?
近年、東京都内や大阪などにはアフリカ料理専門店が増えており、フフを提供するお店も少しずつ増えてきました。多くの場合、フフ+スープ(チキン、フィッシュなど)セットで1,500円〜2,000円程度で提供されています。
また、SNSを通じて在日アフリカ人による家庭料理イベントや、料理教室も開催されており、直接触れる機会も増えています。
もし自宅で試したい場合は、
-
輸入食材店(オンライン可)でフフ粉を購入
-
スープは市販のトマトソースやピーナッツバターなどで代用可能
-
食感の再現を意識して“噛まずに飲み込む”スタイルを体験
👉 文化と料理をセットで体験することで、ただの“グルメ”を超えた食の楽しみ方が広がります。
→第③節フフとは?どこの国の料理?どこで食べられるか?関東で本場の味が楽しめるお店を徹底紹介続く!
③フフとは?どこの国の料理?どこで食べられるか?関東で本場の味が楽しめるお店を徹底紹介
「フフとはどこで食べられるの?」そんな疑問にお応えするため、この記事では西アフリカの主食・フフを日本、特に関東圏で味わえる本格アフリカ料理店をご紹介します。フフとはキャッサバやヤムイモを使った伝統的な主食で、スープに浸して手で食べるのが特徴。本場ガーナやナイジェリア出身のシェフが作る料理を、東京で気軽に体験できます。
関東でフフが食べられるお店3選
1. アフリカンホームタッチ(六本木・東京)
お店のホームページはこちら→https://www.africanhometouch.com/
出身国:ガーナ
アクセス:六本木駅 徒歩5分
六本木にある「アフリカンホームタッチ」は、ガーナ人シェフが腕をふるう本格派アフリカ料理店です。名物料理の「フフ&ピーナッツスープ」は、クリーミーでコクのあるスープが特徴で、もちもちのフフとの相性が抜群。さらに、ビターリーフスープやティラピアスープ、クロコダイル串など他ではなかなか味わえないメニューも豊富です。
おすすめポイント:
- 現地ガーナ人シェフが調理
- アフリカ直輸入のスパイス使用
- メディア掲載多数、雰囲気も本場そのもの
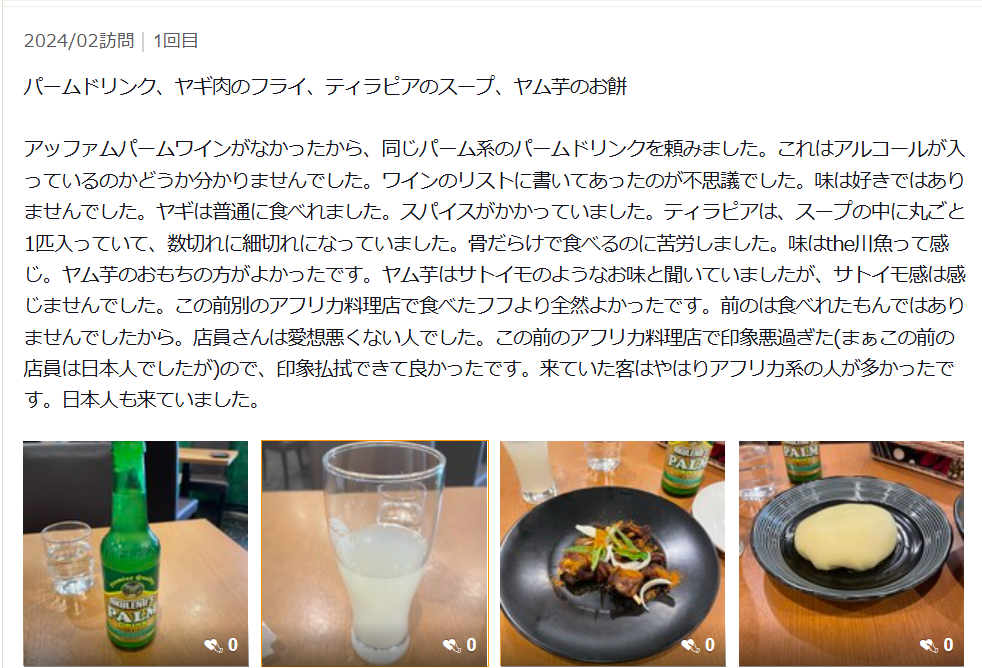

(出典:食べログ、口コミより)
2. アフリカン食堂サバンナ(田町・東京)
お店についてはこちら→https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13145341/?msockid=147bb4a12bc061da2effa15a2aba608e(食べログより)
出身国:ガーナ
アクセス:田町駅 徒歩8分
「アフリカン食堂サバンナ」は、ガーナ人シェフが作る家庭的なアフリカ料理が評判の一軒です。フフとスープのセット(約1,200円)は、ランチでも気軽に楽しめるメニューとして人気。エグシスープやオクラスープ、ジョロフライスといった本場の味が揃っており、日本人にも食べやすい味付けがされています。
おすすめポイント:
- ランチ営業あり、手軽に本場の味が体験可能
- アットホームな雰囲気
- 現地の味を忠実に再現
3. エソギエ(新宿三丁目・東京)
お店のホームページはこちら→https://esogie.com/
出身国:ナイジェリア
アクセス:新宿三丁目駅 徒歩3分
ナイジェリア出身のオーナーが営む「エソギエ」では、手で食べる文化を体験できるのが特徴です。エマ(フフの一種)とともにエグシシチューやティラピアの煮込みなどが楽しめます。手食スタイル用の手洗いセットも用意され、文化体験としても魅力的なレストランです。
おすすめポイント:
- ナイジェリアの家庭料理をそのまま体験
- 音楽やライブイベントも充実
- 食事以上の“文化”を楽しめる

出典:食べログ、口コミより)
まとめ:料理を超えた文化体験としてのフフ
関東には、現地出身者が運営する本格アフリカ料理店が増えつつあります。フフはただの料理ではなく、その土地の文化や人々の暮らしが詰まった存在。六本木の「アフリカンホームタッチ」、田町の「アフリカン食堂サバンナ」、新宿三丁目の「エソギエ」など、東京には味だけでなく雰囲気まで楽しめる名店が揃っています。
「どこの国の料理?」という疑問から始まったフフの世界。今では日本にいながら、本場の味と空気を五感で楽しめる時代です。ぜひ気軽に足を運んで、あなた自身の“アフリカンフード体験”をしてみてください。
総括:フフとは?どこの国の料理?どこで食べられるのか──関東で“本場”の味と文化に出会う旅へ
「フフとはどこの国の料理?」という問いから始まり、実際に日本で食べられる場所を探していく中で、私たちは単なる“料理”を超えた「文化」と出会うことになります。フフとは、ガーナやナイジェリアなどの西アフリカ諸国において、日々の食卓に並ぶ主食であり、家族や仲間とのつながりを象徴する“心の料理”でもあります。
この記事では、関東圏、特に東京都内で本格的なフフを味わえる3つの名店──「アフリカンホームタッチ(六本木)」「アフリカン食堂サバンナ(田町)」「エソギエ(新宿三丁目)」を紹介しました。これらの店はいずれも、単に料理を提供するだけではなく、現地出身者による“文化の伝達”としての役割も果たしています。
六本木の「アフリカンホームタッチ」は、本場ガーナの味をそのままに、ピーナッツスープやビターリーフスープといった伝統的なスープと組み合わせたフフを味わえる名店です。ここではクロコダイルやホロホロ鳥といった日本ではなかなか食べられない珍しい食材も体験でき、フフの懐の深さを改めて実感できます。まさに「フフとは何か」を五感で学べるスポットと言えるでしょう。
一方、田町の「アフリカン食堂サバンナ」は、より日常に近い形でフフと向き合える場所。ランチタイムでも気軽に立ち寄れ、家庭の温もりが感じられるフフやスープが提供されます。ガーナ人シェフの繊細な味付けは、日本人の舌にも合うよう工夫されており、アフリカ料理初心者にもおすすめです。
そして、新宿三丁目の「エソギエ」は、ナイジェリア文化に深く触れられるユニークなレストランです。ラッキーさんというナイジェリア人オーナーが営むこのお店では、ナイジェリア式の手食を体験でき、料理だけでなく、文化・マナー・音楽といった“生活”ごと味わえます。エグシスープやティラピアといった本格料理と共に、心地よいアフリカ音楽が流れる店内はまるで現地の家庭に招かれたかのよう。まさに“体験型アフリカンレストラン”と呼ぶにふさわしい場所です。
フフとは何か。それは単なる“もち状の炭水化物”ではなく、素材・調理法・食べ方・スープの種類に至るまで、アフリカの土地や人々の営みを映す、ひとつの文化体系なのです。そのため、どこの国の料理なのかを知るだけでは不十分で、「どのように提供されるか」「誰が作っているか」「どのような場で食べられているか」を含めて体験することが、本質的な理解に繋がります。
東京には、そうした“文化丸ごと”を提供してくれる店が確実に存在しています。グルメとしての魅力だけでなく、異文化理解や人と人とのつながりに触れる場として、フフは日本の都市生活に新しい味わいをもたらしてくれるでしょう。
もしこの記事を読んで「フフを食べてみたい」と思ったなら、ぜひ一歩踏み出して、実際にお店を訪れてみてください。そこには、料理以上の出会いと発見が待っているはずです。
記事中で紹介した「アフリカンホームタッチ(六本木)」「エソギエ(新宿三丁目)」では、フフと合わせてウガリという東アフリカを中心に広く食べられている主食のひとつで、トウモロコシの粉をお湯で練って作る、シンプルながら非常に重要な料理がとても有名です。ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ザンビアなど多くの国で日常的に食べられています。こちらのウガリに関しても記事を書いているのでぜひ読んでみてください!!
≫≫≫「ウガリはまずい」は誤解? 東アフリカの主食“ウガリ”の魅力と美味しい食べ方

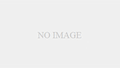

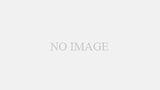
コメント